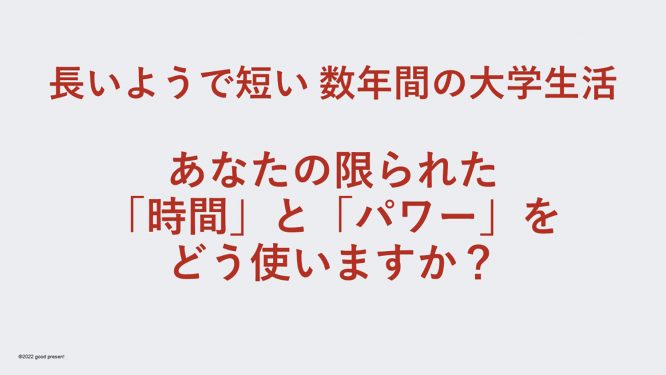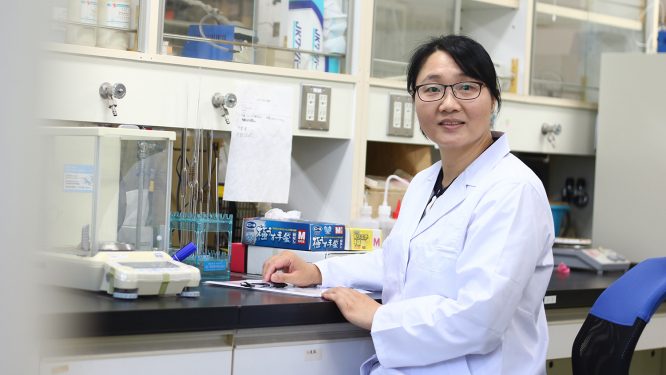「わたしのもの」と「みんなのもの」
新潟大学教員によるコラム"知見と生活のあいだ"
皆さんは「所有権」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?私が専門とする民法には、次のような条文があります。「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」(民法206条)。つまり、私たちは原則として、自分が所有している物をいかように使ってもよいとされており、自分の自転車に乗ったり、自分の本を読んだりするばかりでなく、その自転車や本を壊したり、破いたりすることも認められる、と解釈することができます。このように、所有者は所有物に対して、他人から口出しをされることなく、絶対的な権利を行使することができるとされており、そのような制度のことを「私的所有」と呼ぶこともあります。このような制度は、現在の私たちの社会における最も基本的な要素であり、約束事であるということができます。自分の家に知らない人が入ることを許さず安心して眠ることができるのも、自分が買ったケーキを横取りしようとする人を追い払うことができるのも、「所有権」や「私的所有」という仕組みが社会全体の約束事となっていればこそ、と考えることができるからです。
これだけ読んでも、きわめて当然のことにすぎないと感じられるかもしれません。しかし、次のような例はどうでしょうか?例えば、オークションで高値がついたり、有名な美術館のコレクションになったりする芸術作品があります。レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」や、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」といった絵画は皆さんもご存知のことと思います。仮に、あなたがそのような著名な絵の所有者になったとして(私にはそのようなお金はありません)、あなたがその絵を壊すことや燃やすことは許されるのでしょうか?修復技術が発達したとしても、残された灰を絵に戻すことはできないでしょう。同じような疑問は、最近ますます問題となっている自然環境についてもいうことができそうです。あなたが持っている山や土地を、あなただけのために好き勝手に使ってもよいのでしょうか?周囲に暮らす人々の生活を考慮する必要性はないのでしょうか?一度壊れたものはなかなか元に戻らないということは、自然環境についても妥当しそうです。


こうして考えてみると、私たちが暮らす社会には、「わたしのもの」の他に「みんなのもの」が存在しているようだ、と考えることができます。現代社会で問題となる様々な事柄は、これまでの所有制度に加えて、「みんなのもの」という観点から考えることができるのではないか、ということが最近の関心事です。
プロフィール
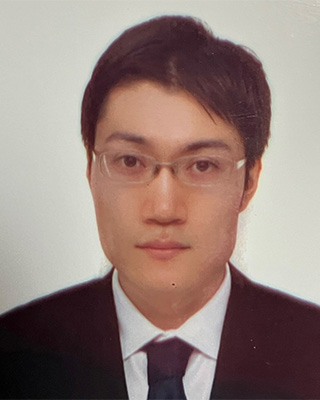
※記事の内容、プロフィール等は2025年3月時点のものです。
関連リンク
タグ(キーワード)
掲載誌
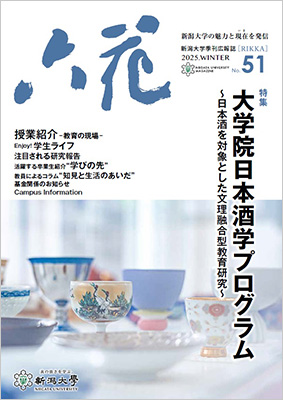
この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第51号にも掲載されています。