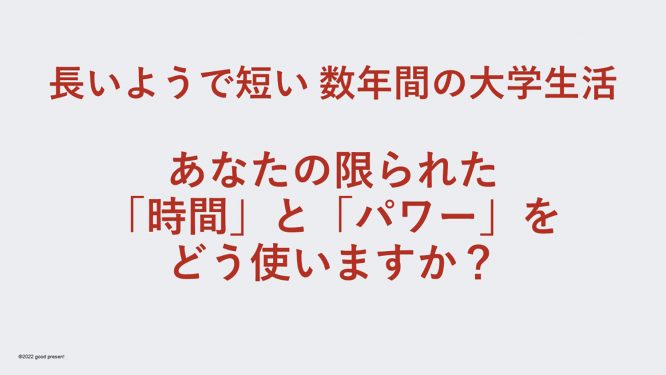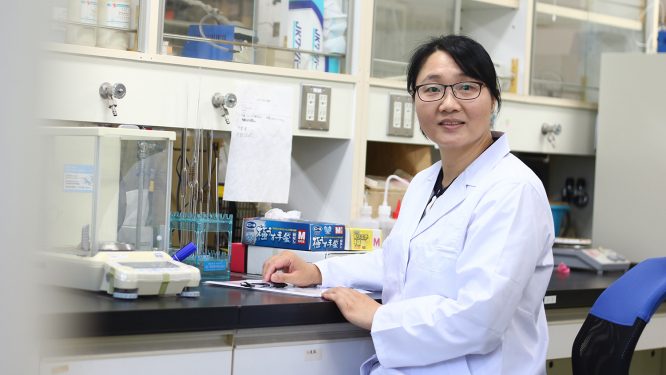白銀の雪原に潜む恐怖
私達の身近で起こる雪氷災害の防減災に向けて
日本は、国土が小さな島国でありながら、世界でもまれに見るほど自然災害が多い国です。どの国でも、地理的条件によって起きやすい災害は違いますが、日本では「被災者生活再建支援法」という法律で、次のように自然災害が定義されています:「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象による被害」。ここには「豪雪」も含まれており、雪や氷による災害は法律上もしっかりと位置づけられています。研究の世界では、雪や氷が関わる現象をまとめて「雪氷(せっぴょう)」と呼んでいます。
「豪雪」と聞いて、みなさんはどんな情景を思い浮かべるでしょうか。白銀の世界や、雪が深々と降り積もる集落を想像されるかもしれません。しかし、国土交通省の資料によると、日本では山陰から近畿、北陸、東北、北海道まで、国土の約半分が「豪雪地帯」に指定されています。さらに近年では、気候変動の影響と考えられる大雪が局地的・極端に起こるようになり、豪雪地帯に限らず全国各地で雪氷災害がほぼ毎年のように発生しています。
日本で起きる雪氷災害は、大雪、屋根雪、着雪、雪崩、吹雪、道路の雪氷の6つに分けられます。私が主に研究しているのは、このうち「吹雪」と「雪崩」です。吹雪では、目の前が見えなくなる視界不良や、道路脇にできる吹きだまり、電線や信号機に雪が付着することで、停電や交通事故などが引き起こされます。一方、雪崩では、登山者やスキーヤーが巻き込まれる事故、道路や橋の破壊、森林の倒木などの被害が起きます。こうした災害の危険度は、自然現象の規模や強さ、人や建物の多さ、防災意識や建物の強さといった要素の組み合わせで決まります。私はその中でも「自然現象を正確に再現・予測すること」に力を入れています。
近年では「ハザードマップ」という言葉を誰もが耳にするようになりました。私の研究の目的を一言でまとめると、「吹雪と雪崩のハザードマップをできるだけ正確につくること」です。つまり、「いつ・どこで・どのくらいの規模で吹雪や雪崩が起こるのか」を地図に落とし込むことを目指しています。そのために、北海道の太平洋側や日本海側での吹雪観測、ニセコでの人工雪崩の実験、新潟県での雪崩調査など、冬の間は全国を飛び回っています。
吹雪の研究を例にとると、重要なのは「風の強さ」と「飛んでいる雪の量」です。これらは高さによって大きく変わるため、風を細かく測る超音波風速計や、雪粒子を数える装置などを使って観測しています。ただし、現地観測だけでは限界もあります。例えば、吹雪は風速や気温である程度予測できますが、雪面の状態によっても変わります。降ったばかりの雪はサラサラで吹き飛ばされやすいのに対し、時間が経つと雪同士がくっついて硬くなり、吹雪が起きにくくなるのです。
観測だけでなく、私は、山形県新庄市にある防災科学技術研究所の「低温風洞」という装置を使った実験も行っています。この装置では一年中人工雪を使え、風の強さや雪面の状態を自由に変えられるため、観測では難しい細かい過程を調べることができます。そして、実験で得られた知見を数式化し、吹雪モデルに組み込むことで、数値シミュレーションの精度が向上します。その結果が実際の吹雪と合っているかを観測データで検証し、より正確なハザードマップの作成につなげています。ただ、モデルを高度化すると、比べるための観測データが存在しないという課題もあります。そのため、新しい観測技術の導入にも取り組み始めています。このように、観測・実験・理論を行き来しながら研究を進めることで、雪氷災害の被害を少しでも減らし、人々の安全に貢献していきたいと考えています。

北海道東部で実施した防雪柵による吹きだまり観測の様子:新しい観測測器を試したところであり、既存の雪氷学の枠組みに囚われないユニークな観測体制を構築しています。

新潟県で発生した雪崩調査の様子:3月になると土砂の混じった雪崩跡が至る所で確認され、その堆積物は数十cmを超える硬い雪塊で構成されています。
プロフィール

新屋啓文
博士(理学)。専門は地球物理学と雪氷学。吹雪や飛砂など粒状体(雪や砂)の移動に伴う自然災害について研究している。広島大学大学院博士課程後期修了後、日本学術振興会特別研究員(PD)、名古屋大学特任助教を経て2018年に新潟大学研究推進機構超域学術院特任助教、2020年に同助教、2022年から新潟大学災害・復興科学研究所准教授。
※記事の内容、プロフィール等は2025年9月時点のものです。