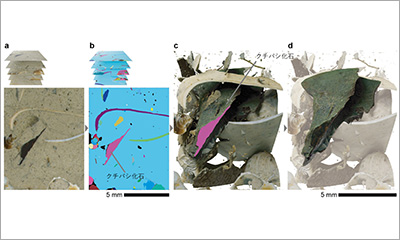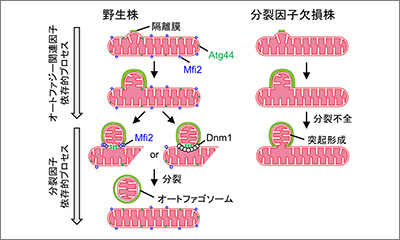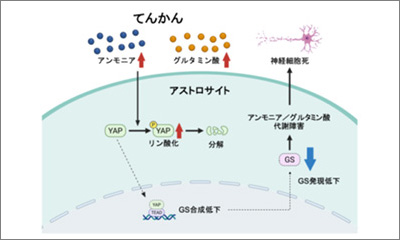蛍光分光法を用いた無花粉スギの簡易識別技術の開発-無花粉スギ実生苗の生産効率化に期待-
本学大学院自然科学研究科博士前期課程の小畑悠さん、農学部の斎藤嘉人助教、森口喜成准教授らの研究グループは、蛍光分光法(注1)を用いた無花粉スギ(注2)の簡易識別技術を開発しました。研究の結果、無花粉(雄性不稔)個体と花粉を飛散させる(可稔)個体では雄花の蛍光特性(注3)が異なり、この違いに注目することで両者を高精度に判別できることが明らかになりました。本研究で得られた知見は、無花粉スギ実生苗を効率的に生産するための簡易識別技術の確立に貢献すると期待されます。
本研究成果は、2025年7月16日に、科学誌「Intelligence, Informatics and Infrastructure」のオンライン版に掲載されました。
本研究成果のポイント
- 雄性不稔個体と可稔個体の励起蛍光マトリクス(EEM)(注4)を取得したところ、両者で異なる蛍光特性が見られました。
- 両者の蛍光特性の違いを効率的に捉えることができる同期蛍光スペクトル(注5)を取得し、蛍光ピーク情報を明瞭にする二次微分処理を行ったスペクトルで判別モデルを作成したところ、テストデータに対して高精度に判別可能である結果となりました。
- 本研究で得られた知見は、無花粉スギ実生苗を効率的に生産するための客観的な簡易識別技術の確立に貢献することが期待されます。
【用語解説】
(注1)蛍光分光法
注3に記載の「蛍光」を分光(波長応答)として計測する手法で、励起波長、蛍光波長に応じた蛍光強度を計測します。
(注2)無花粉スギ
学術的には雄性不稔スギと言います。雄花はつけますが正常な花粉を作りません。雌花は正常に種子を作ることができます。
(注3)蛍光
光を照射すると、分子が光エネルギーを吸収することで安定していたエネルギー状態(基底状態)が不安定なエネルギー状態(励起状態)に遷移します。その後、基底状態に戻ろうとする際にエネルギーを光として放出する現象を発光と呼びます。この時、発光する波長は励起波長よりも長くなります。発光の中でも、一重項状態から励起状態へ遷移する間にのみ光を発するものを蛍光と呼びます。
(注4)励起蛍光マトリクス(EEM)
励起波長、蛍光波長、蛍光強度からなる3次元データで、対象物の蛍光特性を網羅的に測定することが可能です。
(注5)同期蛍光スペクトル
励起波長と蛍光波長の差が一定のスペクトルです。同期蛍光スペクトルは、EEM上で斜め方向に蛍光ピークが広がっていたり、複数のピークが見られたりする場合に効果的と考えられます。
研究内容の詳細
蛍光分光法を用いた無花粉スギの簡易識別技術の開発-無花粉スギ実生苗の生産効率化に期待-(PDF:1MB)
【掲載誌】Intelligence, Informatics and Infrastructure
【論文タイトル】Discrimination between male-sterility and male-fertility in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) using fluorescence spectroscopy.
【著者】Yu Obata1, Takumi Murai2, Yusuke Iida2, Yoshinari Moriguchi3, Yoshito Saito3,*
1 Graduate School of Science and Technology, Niigata University
2 Faculty of Engineering, Niigata University
3 Faculty of Agriculture, Niigata University
*) Corresponding author
【doi】10.11532/jsceiiai.6.2_13
本件に関するお問い合わせ先
広報事務室
E-mail pr-office@adm.niigata-u.ac.jp