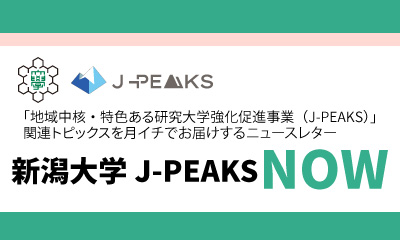「ぼうさいこくたい2025in新潟」セッションS-20
にいがたの産官学民プロジェクトが考える 〜防災気象情報を防災・減災の活動にどう活かすか~を開催しました
防災推進国民大会(通称・ぼうさいこくたい)は、2025年9月6日(土)・7日(日)に、内閣府・新潟県が主催し朱鷺メッセで開催されました。これは、産学官民の関係者が、日頃から行っている防災活動を発表・共有し、交流する日本最大級の防災イベントです。第10回となる今回は約1万9千人が参加し、大いににぎわいました。
新潟大学では、危機管理センターが事務局となり、セッションッションS-20「にいがたの産官学民プロジェクトが考える 〜防災気象情報を防災・減災の活動にどう活かすか~」を開催し、地域住民や防災関係者などおよそ77名の方々が参加しました。
本セッションにおいては、まずは、理工人社、農、医療分野の新潟大研究者が、連携団体との関わり・事例を含め、総合大学の強みをいかした活動を紹介しました。
新潟大学における連携団体との活動紹介
- 災害復興科学研究所の卜部厚志教授からは「地域力創造のための防減災学の試み」は理学の知恵を基盤にいかに地域とつながるかを模索している活動状況が報告されました
- 農学部の藤村忍教授からは「災害への食の備え」について、食品の機能である1)栄養価、2)おいしさ、3)健康機能維持、の3点からいかに考えるべきか、研究成果の社会実装としての「おもいやり災害食認証制度」の創設について紹介されました
- 医歯学総合研究科の高橋昌特任教授からは災害時やリスクが顕在化したときは「臨床医学」「基礎医学」はもちろんのこと、社会状況の関わりの中で対応を考える「社会医学的アプローチ」の重要性が述べられました
続いて、新潟地方気象台から、「防災気象情報を防災・減災の活動にどう活かすか」をテーマに話題提供がありました。
気象台からの話題提供
菅野能明台長からは、防災気象情報の体系と警戒レベルの関係について紹介があり、令和8年出水期から開始する予定の新しい防災気象情報や、線状降水帯に関する情報提供の改善内容が共有されました。
最後に、登壇者による総合討論を行いました。
パネルディスカッション
危機管理センターの田村圭子教授をモデレーターに、それぞれの立場から防災気象情報の利活用について活発な議論を交わしました。
本学では、新潟地方気象台とも引き続き連携を深めながら、産官学民の連携の、地域の防災力向上に向けた取組を継続してまいります。
「ぼうさいこくたい2025in新潟」セッションS-20アーカイブ動画

当日の様子

総合討論の様子
本件に関するお問い合わせ先
危機管理本部危機管理センター
E-mail rmo.jimu@gmail.com